中学生になると、友達と街のお祭りやショッピングに出かける機会が増えますよね。
「おこづかいっていくらが妥当?」「帰りの時間は何時までにする?」と悩む親御さんも多いはず。
我が家の中学2年生の娘も、昨日は友達とお祭りにお出かけ。
おこづかいや門限のルールを改めて考えるきっかけになりました。
この記事では、我が家のおこづかいルールやお祭りの日の特別対応、実際にあった“ヘアオイル事件”から学んだお金の教育についてまとめました。さらに、中学生のおこづかい事情(全国平均データ)も紹介します。
我が家のおこづかいルール
基本は月5,000円、必要と欲しいの線引きを明確に
我が家では、月々のおこづかいは5,000円にしています。
そのうち、
- 必要な物(学校や生活に必須なもの)は親が負担。
- “欲しい物”は相談のうえで購入可否を決定。
- イベントや食事会は、事前相談があれば半額をサポート。
- 毎月1日がおこづかい日。前月のおこづかい帳の提出と引き換えに現金渡し。
「相談ベース」のルールで、お金の使い道を一緒に考える習慣をつけています。
そして、記録する事で現金をきちんと把握できるようにしています。また提出期日を守るように!
お祭りの日のおこづかい、いくら渡す?
中学生の平均おこづかいデータ
全国調査(小遣い帳アプリZaimの調べ)によると、
中学生のおこづかい平均額は月2,500〜3,000円だそうです。
イベントやお祭りでは、+1,000〜2,000円程度を臨時で渡す家庭が多いようですね。
我が家の場合:2,000円を追加
今回は、娘に2,000円の“お祭り特別おこづかい”をプラスしました。
屋台で焼きそばやかき氷を楽しんで、ちょっとした小物も買えるくらいの金額です。
ここ最近の物価高の影響もあり悩みましたが、買い物ついでに下見に行き、金額を決めました。
帰宅時間(門限)はどうする?
お祭りの日は20時までOK
普段の我が家の門限は19時にしています。
でも、お祭りは夜が盛り上がるので特例で20時までOKにしました。
ただし、何かあった際、万が一遅れる時は必ず連絡することと念押ししました。
ヘアオイル事件で感じた「お金の教育の難しさ」
今日は、お祭り帰りに娘から、
「ヘアオイルを買ったからお金ちょうだい」
と言われました。
でも、事前に相談がなかった“欲しい物”なのでルール上はNGです。
どうも、買ってもらえると思っていたようです。
娘は「一緒にいたら買ってもらえたかもしれないじゃん」と不満げでしたが、
結果が同じでも、過程が大事。相談して納得することが大切だよね。
欲しいなと思ったなら、電話して確認する事もできたんじゃない?
何の相談も無しに買ったからお金欲しいはちょっと順番が違うかな?
と話しました。
このやりとりは、お金の使い方を学ぶ良いきっかけになったと思います。
中学生ぐらいなら分かっているかなと思うことも、こうして実際のやり取りがあると学びの機会になります。
確かに、一緒にドラッグストアに行っている時に、これ欲しいなと言われ、今使ってるオイルがもう少しで無くなるんだよねと言われていたら買ってあげていた可能性はあります。
娘はどうやら結果だけに着目したようですが、今回の話はきちんと理解できたでしょうか?
また次のお買い物事件が起きない事を祈りつつ見守っていきたいと思います。
おこづかいルールは“家庭ごとの正解”を見つける
おこづかいは単なるお金ではなく、
- 計画的に使う力
- 自分で選ぶ責任感
を育てる教材だと思います。
金額やルールに正解はありませんが、「親子で話し合って決める」ことが最大のポイントです。
まとめ
- 中学生のおこづかい平均は月2,500〜3,000円。お祭りの臨時は+1,000〜2,000円が目安。
- 門限は19〜20時が多い。安全対策も忘れずに。
- “事前相談”を通じてお金の価値を学ぶことが大切。
お金の教育に参考になる本
おこづかいルール作りや金銭感覚の育て方に悩むとき、親子で読める本を参考にするのもおすすめです。
- 『10歳から知っておきたいお金の心得』(岩崎書店)
子どもが楽しく学べるイラスト豊富な入門書。おこづかい帳のつけ方や貯金のコツもわかりやすい。
- 『中学生から身につけておきたい賢く生きるための金融リテラシー』(ジャムハウス出版)
お金の成り立ちから家計管理まで、幅広くお金にまつわる知識を学べる中高生向けの書籍です。
- 『お金の教育がすべて。』(村田幸紀/サンマーク出版)
親が知っておくべき「お金の考え方」を体系的に学べる。親向けの参考書。
本をきっかけに、親子で「お金の使い方・貯め方・増やし方」について話す時間をつくると、家庭での金銭教育がよりスムーズになります。
あなたの家庭ではどうしていますか?
中学生のおこづかい、いくら渡していますか?
お祭りや特別な日のルールは?
「欲しい物」と「必要な物」の線引きはどうしてますか?
ぜひこの機会に親子で話し合ってみてください。
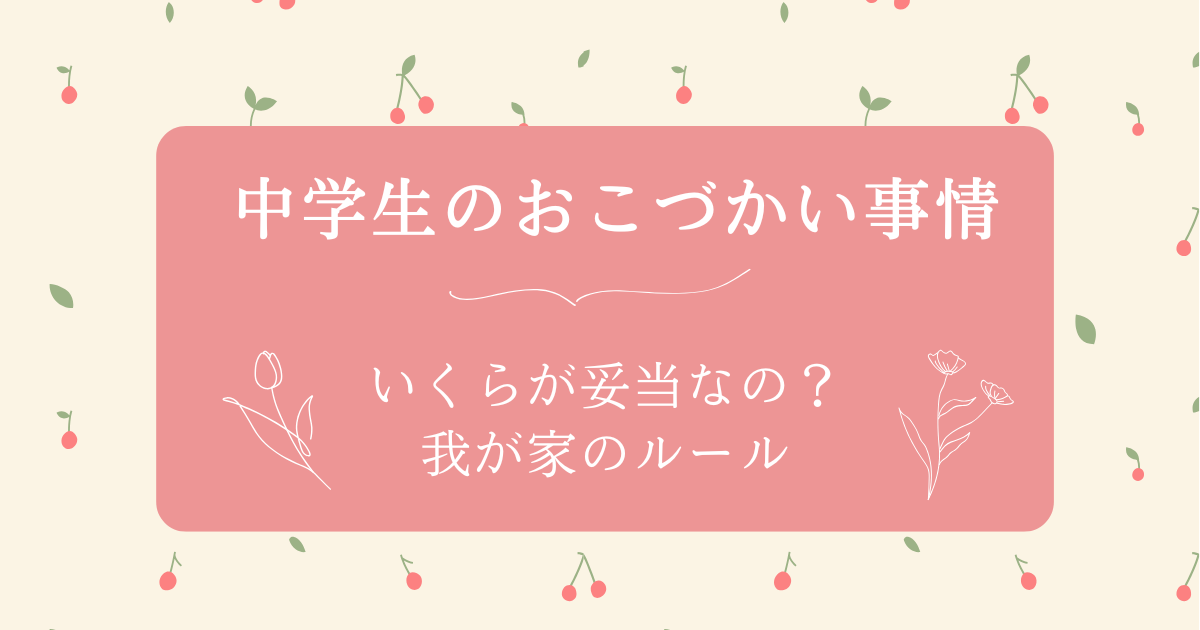
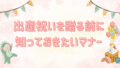
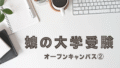
コメント